
診療科紹介
当院整形外科にて治療を行っている症状
- 首の痛み、腰の痛み、肩の痛み、膝の痛み
- 手足のしびれ
- 関節の変形・腫れ
- 骨折、打撲、脱臼などの外傷
- 傷の処置
- 捻挫、突き指、肉離れなどのスポーツ外傷
- 運動後の肩、肘、膝、腰の痛みなどのスポーツ障害
- 骨粗鬆症の診断、治療
- 交通事故後の首や腰の痛み
- 体にできたできもの
主な疾患に対する治療
変形性膝関節症
歩行時や階段昇降時の膝の痛みで受診されることが多い疾患です。
日本人の場合、多くは膝の内側の軟骨のすり減りから始まることが多いため、膝の内側の痛みを訴えられることも特徴です。
レントゲン写真のみでの診断も可能ですが、痛みが強い場合や関節の中に水がよくたまる方にはMRIで精密検査を行っております。
鎮痛薬や外用薬による治療と膝周辺の筋肉の強化・可動域訓練などのリハビリを基本とし、症状に応じて膝の関節の中にヒアルロン酸という滑りを良くする薬を注射して治療を行います。
腰部脊柱管狭窄症
腰痛や歩行時の足のだるさや痛みで受診さることが多い疾患です。
歩行していると足が痛くなったりしびれたりするため、休むとまた歩けるようになるのが特徴です。
腰の神経の通り道が年齢とともに狭くなることにより症状が出現します。
腰椎のレントゲン写真で推測可能な場合もありますが、確定診断のためにMRIの撮影を行い、神経の通り道が狭くなっていることを確認しております。
脊髄の血流をよくする薬や神経痛を抑える薬による内服加療とストレッチやマッサージなどのリハビリを組み合わせて治療します。
骨粗鬆症
女性の方は閉経すると程度の差はあれ、骨粗鬆症になる可能性があります。
骨粗鬆症に自覚症状はありませんが、転んだときなどに背骨や股関節の骨折を起こして手術が必要になったり、最悪寝たきりになったりするため、症状がなくても判明した時点で治療が必要です。
当院ではデキサ法という骨密度測定法を用いてより正確に測定を行っております。
骨密度、これまでの骨折の有無、年齢などによって治療方針を決定いたします。
野球肘・野球肩
小学校高学年、中学生くらいの野球少年に多く生じ、投球時の肘の痛みや肩の痛みで受診されます。
多くの場合は、投球フォームの悪さや、投げすぎが原因となります。
当院ではレントゲン検査、超音波検査により診断を行い、必要に応じてMRIを追加で行っております。
診断がついた場合、投球を一定期間中止し、痛みが治まってから当院の理学療法士の指導の元、徐々に投球を再開していくこととなります。 安静とその後のリハビリによる投球フォームの改善により改善が見込めるため、早期に受診していただくことが大切になります。
頸椎椎間板ヘルニア
手や腕の痛み、箸が使えない、ボタンがしめられないなどの症状で受診される方が多い疾患です。
首の骨の間にある椎間板というクッション材が飛び出して、首の神経の通り道を圧迫することで症状が起こります。
レントゲン検査では、骨しか見ることが出来ないため、診察でこの疾患が疑わしい方にはMRI撮影をすすめております。
MRIであれば、椎間板や神経の通り道の評価が可能となります。
頸椎椎間板ヘルニアは手術を行わない保存療法が基本となります。
鎮痛薬や神経痛を抑える薬を内服し、頸椎牽引などのリハビリを行っていただいて治療を行います。
腰椎椎間板ヘルニア
足のしびれや痛み、腰痛などの症状で受診されることが多い疾患です。
腰の骨の間にある椎間板というクッション材が飛び出して、腰の神経の通り道を圧迫することで症状が起こります。
頸椎椎間板ヘルニアと同じく、レントゲン検査では骨しか見ることが出来ないため、疑わしい方にはMRI撮影をすすめております。
腰椎椎間板ヘルニアの治療も手術を行わない保存療法が基本となります。
鎮痛薬や神経痛を抑える薬を内服し、腰椎牽引などのリハビリを行っていただいて治療を行います。
関節リウマチ
手指や足指の関節の腫れや痛み、こわばり感で受診されることが多い疾患です。
女性の方に多く起こり、確実な原因はわかっていないのが現状です。
ご家族に関節リウマチの方がいるなど、家族歴がある場合もあります。
放置すると関節の変形が進むため、早期に診断をすることが重要です。
当院ではレントゲン検査、採血を行って診断するとともに、関節の超音波検査を行って関節リウマチの状態の評価を行っております。
関節リウマチと診断した場合には、消炎鎮痛薬や抗リウマチ薬を使用して関節リウマチの進行を抑制します。
筋膜性疼痛
近年日本でも広がりつつある概念になります。
日本の整形外科ではレントゲンやMRIで視覚的に評価可能な骨、関節、神経に痛みの原因を求める傾向にありました。
しかし、レントゲンやMRIでは異常がないにも関わらず、痛みやしびれを訴える方が多くいらっしゃいます。
そのような方の痛みには筋肉の血流不良やその結果起こる硬さが原因と考えられる場合もあります。
肩こりや腰痛、頸椎椎間板ヘルニア・腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症と診断されたにも関わらず治らない手足の痛みやしびれはこれが原因である可能性もあります。
そのような場合にはトリガーポイント注射という注射を筋肉に行って硬さを取って血行を促進し、同時にリハビリを行って筋肉のこりをほぐしていくことで改善を期待することができます。
主に下記の疾患・症状の診断、治療、予防を行っています。
- 頭痛
- 脳血管障害(脳内出血、くも膜下出血、脳動静脈奇形、脳梗塞、もやもや病 等)
- 頭蓋内腫瘍
- 頭部外傷
- パーキンソン病、パーキンソン症候群
- めまい、進行する聴力障害や耳鳴り、半側顔面痙攣(顔半分のけいれん)
- しびれ、痛み
- てんかん
- 認知症
外来では脳神経外科的な疾患はすべてお受けしています。しかし当院では手術は行っていません。
したがって手術を要する疾患が診断されたら近隣の脳外科のある病院に紹介します。脳神経外科としてよく使う検査はMRI、CT(系列病院にて検査 )、超音波頸動脈撮影、脳波検査などがあります。
クリニックにて「脳ドック」を実施しております。
詳細はこちら。
外来リハビリテーション
1階リハビリテーション室(主な対象:運動器疾患/脳血管疾患等)
主な症状
肩こり、頚部痛、腰痛、ねんざ、骨折、しびれ、夜間痛、スポーツ外傷、交通事故、歩行が不安定など
リハビリ実績
頚椎症、頸椎椎間板ヘルニア、肩関節周囲炎、橈骨遠位端骨折、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、 腰椎分離症、変形性膝関節症、前十字靭帯損傷、オスグット病、前距腓靭帯損傷、野球肩・肘、 脳梗塞、脳出血、パーキンソン病、など

当院の外来リハビリの特徴は「担当制」「完全予約制」「自己管理」です。
- 理学療法士、作業療法士の国家資格を持つリハビリの専門家が担当制にてリハビリのゴールに向かって寄り添います。
- 1回のリハビリ時間は20~40分です。完全予約制なので待ち時間は殆どありません。
- 疼痛をコントロールする目的で行われる徒手療法・物理療法もありますが、自主トレーニングの指導や動作方法の訓練を受けることで最終的に自己管理できること=病院へ通わなくて良くなることを目指します。

リハビリテーションの実施には医師の処方が必要となります。
詳しくは整形外科、脳神経科の医師へご相談下さい。
野球ひじ・野球肩専門外来
野球ひじ・野球肩は関節軟骨や靭帯、筋肉の炎症が起きているケガ・スポーツ障害です。
当院では診察・検査・リハビリで連携し、治療からスポーツ復帰までサポートをさせて頂きます。
お気軽にご連絡をお待ちしております。
※PULSE Throw(パルススロー)とは、投球側の肘(ひじ)にセンサーを装着し、投球動作時の肘への負担を数値化できる機器です。
当院ではリハビリの際、実際に投球を行いながら計測することが可能です。
4階リハビリテーション室(主な対象:子どもの発達に関わる疾患)
お知らせ
- 言語療法STについて
平日11時・14時の予約枠に空きがあります。 - 作業療法OTについて
平日10時・11時・13時・14時の予約に空きがあります。
※言語療法ST・作業療法OTにつきましてはリハビリ初回から5回は限定された時間内の予約になり、6回目以降は他の 時間帯でも予約が取れるように調整します。新規で言語療法ST、作業療法OTを希望であり、上記の時間帯に月2回は通院が可能である方は当院までお問い合わせください。
※言語療法ST・作業療法OTにつきましては、新規対象年齢を小学校1年生までとさせていただきます。
- 理学療法PTについて
平日9時~18時までの間、予約枠に空きがあります。
歩行練習、関節可動域訓練など、身体障害をもつ15歳までの小児に対応しています。
側弯などでお悩みの方もご相談ください。
受付開始日:令和7年 3月 25日(火曜日)
受付時間:9:00~18:00
お問い合わせ番号:0563-54-5794(小児リハビリテーション直通番号) へ
はぐくみ ペアレントトレーニング 開催案内
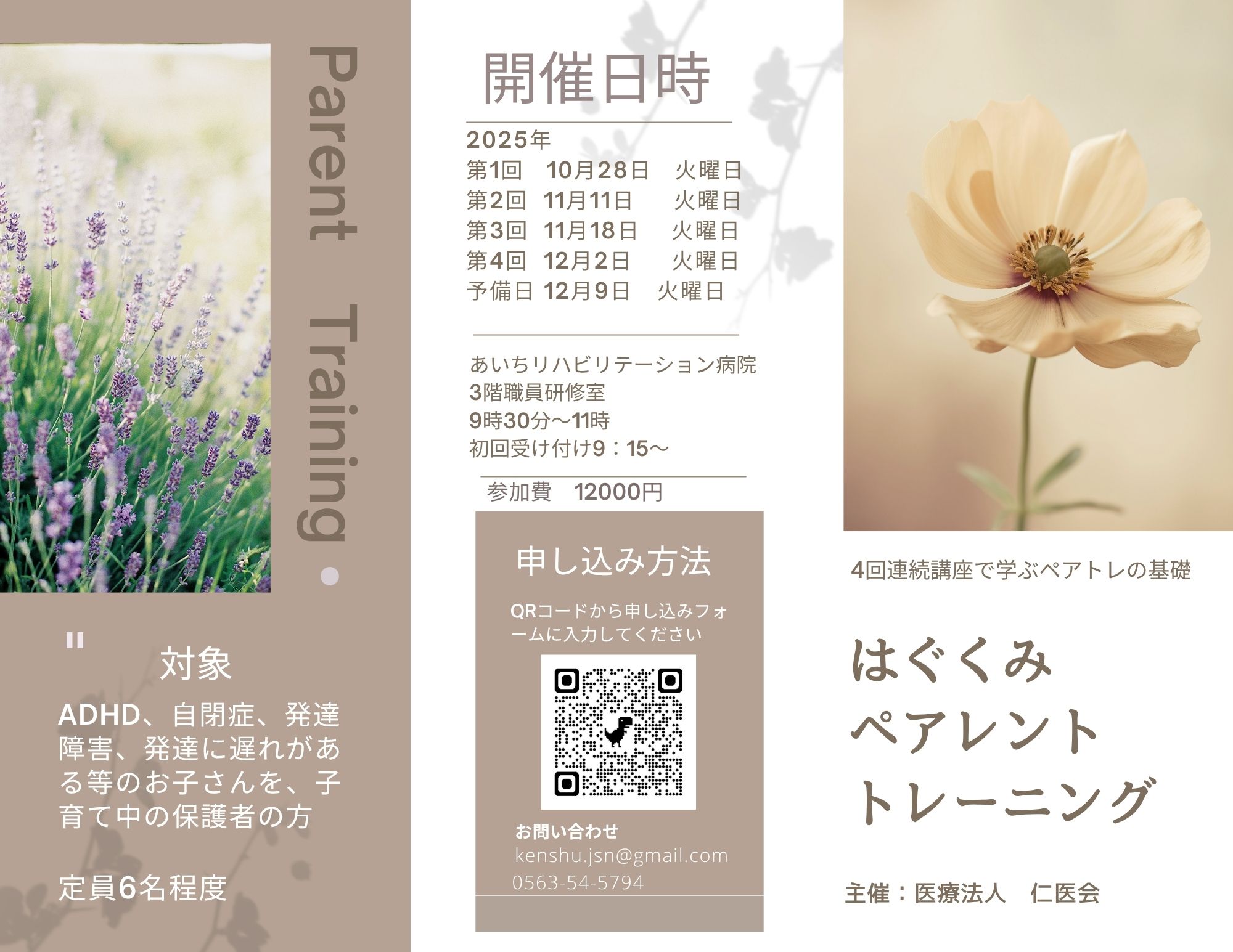

ペアレントトレーニングのご案内 10月開催 申し込みはこちらをご利用下さい
小児リハビリテーション・診察のご案内
当院では子どもの成長とともにご家族・教育機関と協力し合いながら、ひとりひとりの子どもに適したリハビリテーションを提供させて頂きます。

言語聴覚士ST、作業療法士OT、理学療法士PTによるリハビリテーション
- 自閉症スペクトラム障害、精神発達遅滞、ダウン症などの子どもの発達に関わる疾患のある方が対象
- 月曜日~金曜日は9:00~18:30、土曜日は9:00~12:30
リハビリ予約は曜日・時間指定はしておりませんので、各担当者とその都度ご相談ください。 - 他院とのリハビリ併用はお断りしております。
※他院で言語療法STを受けている場合、当院で言語療法STは受けられません。しかし、必要であれば作業療法を受けることは可能です。
- 諸事情により当院へ移行したい場合は診察時にご相談ください。
- リハビリの移行が確定した後、前担当者による情報提供書の提出をお願いしております。
臨床心理士による面接・検査のご案内
- 医師の診察と合わせて、臨床心理士(公認心理士)による発達相談、カウンセリング、知能検査などの保険診療に各種対応しております。
- 保険診療のカウンセリングの対象は、発達障害、不登校、ストレス関連疾患等でお困りの、小学生以下とさせていただいています。
- 臨床心理士(公認心理師)による、自費診療のカウンセリングも行っています。
- 自費診療は、18歳もしくは高等学校卒業時までの子ども、またはその保護者を対象としています。
| 自費診療の料金について | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発達検査・知能検査 | 発達相談 (18歳もしくは高等学校卒業時までの子ども、 またはその保護者を対象としています) |
|||||
| 1日目 | 検査(1種類) | 4000円 | 1回 | 50分 | 4000円 | |
| 2日目 | 検査結果の報告面接 | 4000円 | ||||
| 報告書のお渡し | 3300円 | |||||
| 合計 11300円 | ||||||
診察・リハビリ・心理検査などのお問い合わせは、小児リハビリテーション室直通番号までご連絡ください。
小児リハビリテーション室直通番号 0563-54-5794
急な病気や体調不良に対する診断・治療・高血圧などといった慢性疾患の継続的な 治療、生活習慣病の改善、予防接種や検診などを行ないます。
クリニックにて「健康診断」を実施しております。
詳細はこちら。
医師のご紹介

院長
中澤 仁 / なかざわ ひとし
| 担当科 | 整形外科 |
|---|---|
| 専門・得意分野 | 運動器障害/リハビリテーション |
| 経歴・所属学会 | 1968年 岩手医科大学卒 身体障害者福祉法第15条 指定医師 |
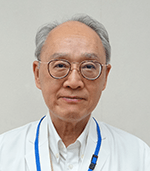
仲野 領二郎 / なかの りょうじろう
| 担当科 | 内科 |
|---|---|
| 経歴・所属学会 | 名古屋保健衛生大学卒 透析専門医 認定内科医 消化器病専門医 腎臓専門医 |



